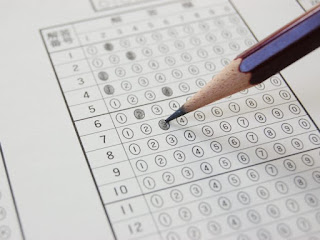高専の学力入試ってどんなの?勉強法は?【明石高専生が解説】
今回は
・高専生の学力入試ってどんなの?
・おすすめの勉強法は?
・おすすめの勉強法は?
といった疑問にこたえていきます。ぜひ最後まで見ていってください。
高専の一般入試
高専は基本的に、推薦入試と一般入試の2種類の入試があります。
推薦入試についてはこちらの記事で解説しています。
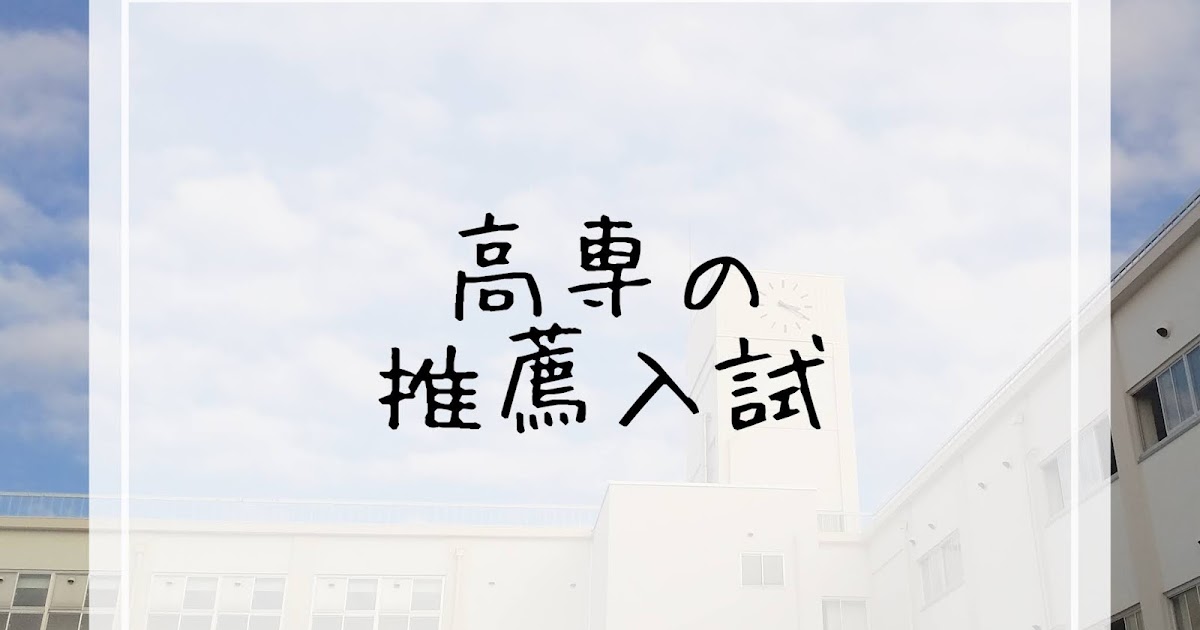
高専の推薦入試ってどんなの?【グループワークについて解説】
こんにちは。現役高専生のさゆです。 今回は 高専の推薦試験ってどんなの? 内申点がどれくらいあれば受かる? という疑問にこたえていきます。ぜひ最後まで見ていってください。
日程
毎年2月中旬の日曜日に行われています。
私の住んでいる地域では公立高校入試が3月なので、もし高専の入試がうまくいかなくても高校入試を受けることができました。
また高専の一般入試の前後では、私立高校の学力入試も受けることができます。
他の同級生よりも早めに進路が決まり、不安な期間が少なく済むのがメリットです。
さらに私の学校ではできませんでしたが、高専によってはそもそも高専と高校を併願してどちらも受験でき、両方合格すれば好きな方に入学できるそうです。
これができる高専では倍率がすごく高くなっていますが、合格者が全員高専に入学するわけではないので、実際の倍率はそこまで高くありません。
問題の形式
解答用紙はマークシート
国立高専と公立高専の学力入試は英数国理社の5科目(学校によっては社会を除いた4科目)で行われる、マークシート式の試験です。
全国の国立高専すべてで同じ日に、同じ内容の試験が行われます。そのため、複数の国公立高専の学力入試を受けることはできません(北海道にある4つの高専は例外)。
配点は各教科100点満点ですが、学校によっては数学と英語を150点満点にするなど、力を入れてほしい教科に重みづけをしています。
また、すべての教科がマークシート式になっています。
なので、自分で考えて書く記述問題や証明問題などは出てきません。そのかわりに、正しい説明を選択肢から選ぶような問題が出されています。
こうして計算された筆記試験の点数に、調査書の点数を加えて合格者を決めます。この調査書の配点は、100点満点の学校もあれば400点満点の学校もあるなど、ばらつきが大きいです。気になっている高専の配点は、試験科目とあわせて学校のホームページから調べてみてください。
推薦入試との違い
私の学校の場合ですが、推薦入試と一般入試で定員の半分ずつが合格します。
また、いつも定員よりも2、3人多く合格しているので、40人が定員のクラスで推薦で21人、一般で21人が合格するようなイメージです。
推薦入試で合格する人が全体の半分というのは、普通の高校と比べてとても多いでしょう。
推薦入試は、内申点で合格かどうかがほぼ決まります。
配点が1000点あるうち、当日の試験で決まるのが18点で、残りの982点はすべて内申点でつけられます。
このように中学校での生活や成績で合格不合格が決まってしまう推薦入試に対して、一般入試は試験の配点が高く、結果次第で内申点が低くても合格できます。
一般入試で合格した人には、推薦入試は落ちてしまったけれどそこそこの内申点だった人はもちろん、中学のころに不登校の期間があったり、課題をほぼ提出していなかったりして内申点がすごく低かった人もいます。
中学の内申点が低くても、高専に向けてすごく努力してきた人や、勉強はできるけれど先生や中学校の雰囲気が合わなかった人は、当日のテストで実力を出して巻き返しているのかなと思います。
そうして合格した人の中には、コンテストで活躍していたり、クラスでトップの成績をとったりしている人もいます。
また、私の学校では一般入試は第2志望、第3志望の学科を選ぶことができました。
ほとんどの年で、電気>機械>建築>都市の順で合格最低点が高いです。
なので、自分が一番受けたい学科を第1志望にして、その学科より合格最低点が低く、自分の興味がある学科があれば第2、第3志望にするといいと思います。
ただ、年によって合格最低点の順番は変わるので、第1志望を機械、第2志望を電気という風にするのも悪くないと思います。
私は機械を第1志望、都市を第2志望にして出願しました。
もちろん、第1志望のみにすることもできます。
高専に行きたいから、という理由で興味のない学科に入ってしまうといつかしんどくなってくると思います。
なので第2、第3志望を選ぶときは、その学科に本当に興味があるか、もしその学科に入っても後悔しないかをよく考えるようにしましょう。
POINT
学力入試で合格するのは定員の半分。
内申点が悪くても、当日の試験次第では合格することも。
第2志望、第3志望の学科も選ぶことができる。
勉強法
過去問は必ず解いておこう
基本は高校受験の勉強をしながら、その合間に過去問や予想問題集などを解いて、形式に慣れていくのがいいと思います。
私は推薦受験で合格したので一般受験は受けなかったのですが、1月末まで試験勉強をしていました。
私の場合、3年生の春から個人塾に通い始めました。そこでは塾のワークが出されて、解いて丸付けをしてもらって、まちがったところを直して、というのをひたすら繰り返す形式で、解いた問題の数を積むことができました。
どの教科も、解いた問題が増えていくとパターンが見えてくるので、成績が伸び悩んでいて入試まで時間がある人にはおすすめです。
夏が過ぎたあたりで、少しずつ過去問を解き始めました。
最初は時間を計らずに解くことに集中してやり始め、形式が分かってきたら時間を計って、本番同様マークシートを用意して解くようにしました。最終的には6年分の問題を3、4回したと思います。
過去3年分の合格最低点はオープンキャンパスで教えてもらったので、5教科解き終わるたびに自分の受ける学科の最低点と比べて、自分がいまどれくらいできてるのかの参考にしていました。
私が使っていたのはこの過去問集です。
リンク
高専機構のホームページに過去問は載っていますが、3年分しかなく、著作権の関係で文章が黒塗りになっている問題がいくつかあります。問題集を買うと黒塗りになっている問題はほとんどありません。
また、この本は高専入試でよく紹介される赤本よりも安く、1年分問題が多い(6年分収録されている)のでおすすめです。
マークシートのページをコピーしてそれに答えを書くようにすると、何度も試験同様に解くことができます。
時間があるときは試験同様に、時間がない時は間違えた問題に事前にチェックを付けておいて、チェックの多い問題から解くと効率的に勉強できます。
また高校入試の模試で、高専を志望校に選んで出た判定はあまり目安にはなりません。
高校入試と高専入試の問題形式が大きく違うからです。
模試の結果よりも、過去問や入試予想問題を解いて、点数が合格最低点の平均よりも高いかどうかを見るほうが実際の力を知ることができると思います。
入試の予想問題は、模試の形式で塾が出しているものもありますが、本も出ています。
リンク
模試と違って順位などは出ませんが、1冊で2回分の予想問題を解くことができるので、本を買ってみるのもいいと思います。
POINT
学力入試の対策は、基本的には高校入試の勉強をすればOK。
高専の過去問や予想問題集も使いながら、問題の形式にも慣れよう。
まとめ
高専の一般入試は当日の試験の配点が大きく、内申点が悪くても実力で巻き返すことができます。推薦入試に落ちてしまった人でも一般で合格した人はたくさんいます。
あなたの受験が成功することを祈っています。
一般入試について他にも知りたい方は、こちらもどうぞ。
他の方のブログですが、明石高専の一般入試について詳しく解説されています。
【知恵袋】明石高専の入試は内申が必要?”現役明石高専生”が徹底解説!『学力編』
【知恵袋】明石高専の入試は内申が必要?”現役明石高専生”が徹底解説!『学力編』
ぜひ他の記事も見ていってくださいね。